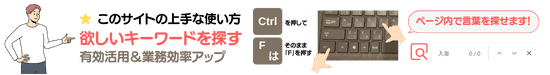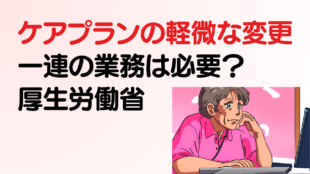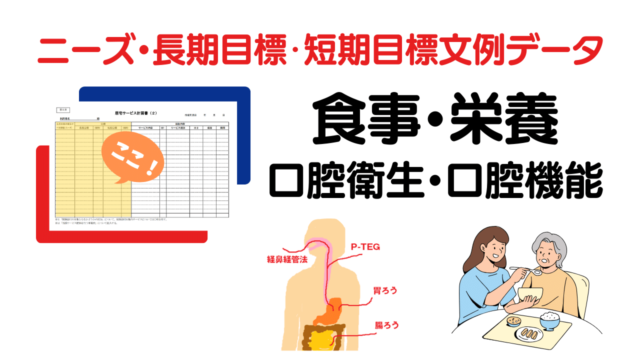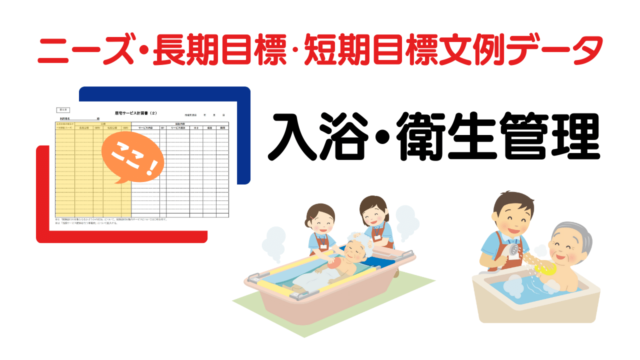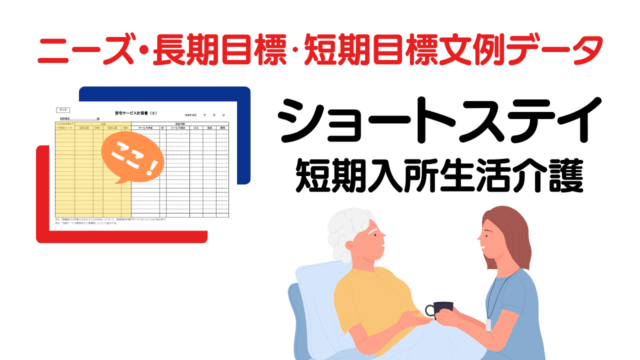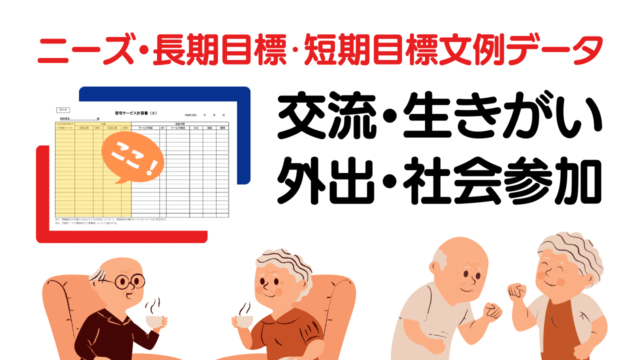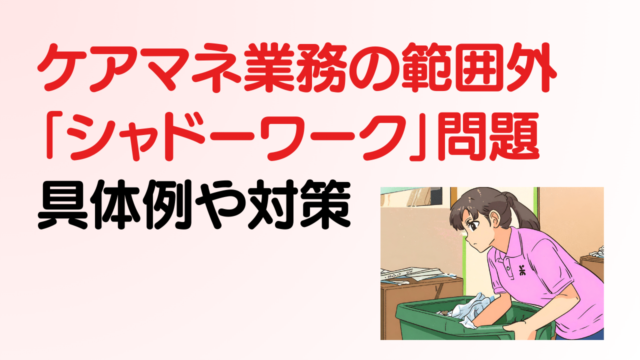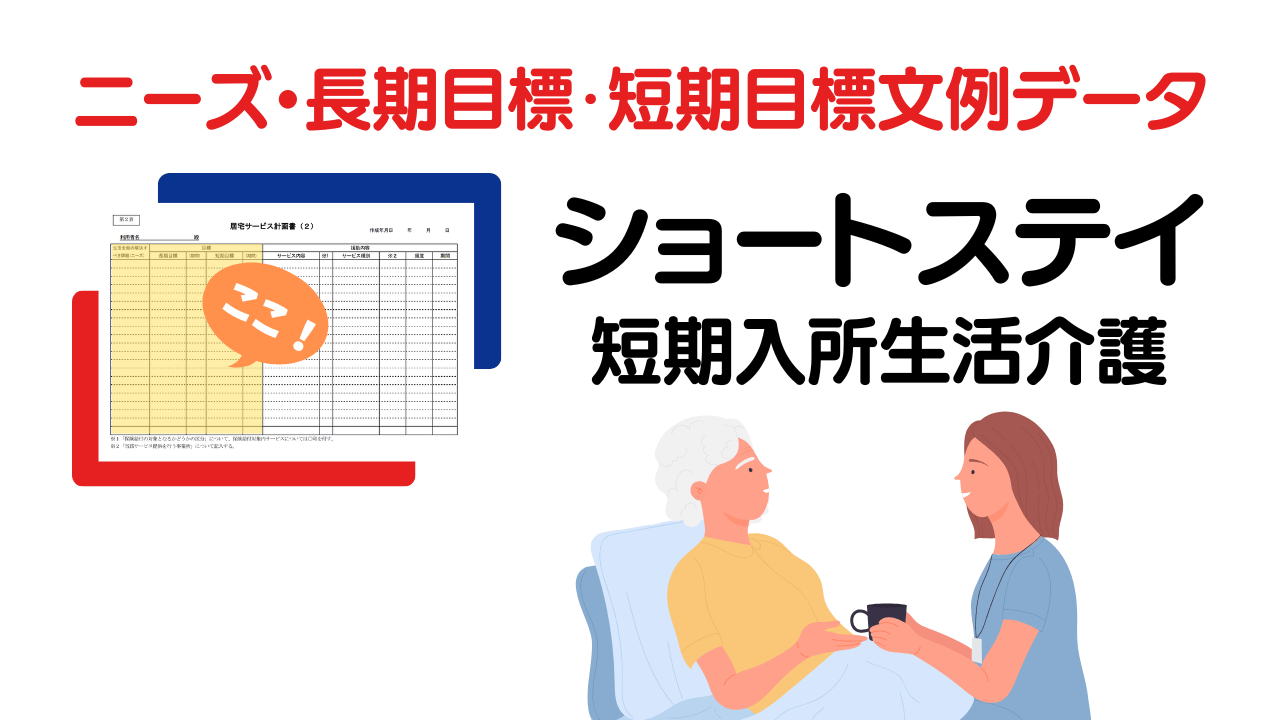
ショートステイは、介護者の休息や在宅生活の継続を支える大切なサービスです。特に認知症や医療的ケアが必要な方、終末期に向かう方、家族との関係に課題があるケースなど、多様な状況に対応するためには、適切なニーズ把握と目標設定が欠かせません。
本記事では、居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅サービス計画書を作成する際に役立つよう、ショートステイ利用に関するニーズ・長期目標・短期目標の文例を100件掲載しています。家族支援や医療的対応、終末期支援など、実際の介護現場で想定されるさまざまなケースに対応できる内容となっています。
ケアプランの具体化に迷ったとき、文章表現に悩んだときの参考としてぜひご活用ください。
本記事で紹介している「ニーズ」は、あくまで利用者本人やご家族の困りごとや希望を中心に捉えています。そのうえで「長期目標」では、本人・家族にとって理想的なゴールをやや広めに設定し、目指す方向性を明確にしています。一方、「短期目標」は、現実的にすぐ取り組める内容へと具体的に落とし込んでおり、実践しやすさを重視しています。また、ケアマネジャーが居宅サービス計画に取り入れやすいように、あえて「〇ヶ月以内に〜する」といった期限付きの目標も多めに設定しています。
介護保険のショートステイ(短期入所生活介護)の役割
介護保険制度における短期入所生活介護(ショートステイ)は、要介護者が可能な限り自宅で自立した日常生活を継続できるよう支援するサービスです。特別養護老人ホームなどの施設に短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活上の介護や機能訓練を受けることで、利用者の心身機能の維持・回復を図ります。また、家族の身体的・精神的負担の軽減も目的としています。
利用対象者は、要介護認定を受けた方で、在宅での生活を基本としながら一時的に施設での支援が必要な場合に利用されます。利用日数は連続30日までと定められており、介護者の休養や冠婚葬祭、出張などの際にも活用されています。このサービスは、在宅介護の継続を支える重要な役割を担っており、利用者と家族の生活の質の向上に寄与しています。
介護保険のショートステイとは?利用可能な期間・費用や減額
介護保険のショートステイ(短期入所生活介護) 30日を超える長期利用
短期入所生活介護においては、長期に利用する場合について以下の規定を設けられています。
- 利用者が連続して30日を超えてサービスを受けている場合においては、30日を超える日以降に受けたサービスについては、短期入所生活介護費を算定することができない。
- 自費利用を挟み同一事業所を連続30日を利用している者に対してサービス提供をする場合には、連続30日を超えた日から減算を行う(1日につき30単位)。
ショートステイ利用に関するニーズ・長期目標・短期目標例文一覧【基本】
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 家族の介護負担を軽減したい | 家族の介護負担が軽減し、家庭内の介護環境を維持できる | 月1回ショートステイを利用し、家族の休養時間を確保する |
| 本人の心身のリフレッシュを図りたい | 本人が気分転換を図り、日常生活に前向きに取り組めるようになる | 3ヶ月以内にショートステイを体験し、楽しかったと感じられるよう支援する |
| 独居で不安なため、宿泊体験に慣れたい | ショートステイ利用を通じて、宿泊に対する不安感が軽減する | 1ヶ月以内に2泊3日のショートステイを体験する |
| 家族が不在時の受け入れ先を確保したい | 緊急時でもショートステイを利用し、安心して生活を継続できる | 2ヶ月以内にショートステイ先との事前契約を済ませる |
| 夜間の介護負担を軽減したい | 夜間の介護負担が減り、家族が十分な休息を取れるようになる | 月2回のショートステイ利用を定着させる |
| 在宅生活を継続したいが、介護疲れを防ぎたい | 在宅生活を維持しながら、家族が継続的に介護できる環境を整える | 2ヶ月以内に定期利用(月1〜2回)を開始する |
| 本人の孤立感を軽減したい | 他者との交流機会が増え、本人の孤立感が改善する | ショートステイ先で他者との交流を1回以上持てるよう支援する |
| 施設生活への不安を少しずつ解消したい | 将来的な施設入所への抵抗感が軽減する | 6ヶ月以内に3回以上のショートステイ体験を行う |
| 生活リズムの維持を図りたい | ショートステイ利用中も規則正しい生活が送れるようになる | 滞在中も起床・食事・就寝時間が守れるように支援する |
| 症状の悪化を防ぎたい(例:認知症進行予防) | 環境の変化に適応し、症状の悪化を防ぎながら生活できる | ショートステイ中も安心して過ごせる支援を行う |
| 介護者の通院・用事のために一時的に預けたい | 介護者の生活や健康管理を支援し、介護継続を可能にする | 必要時にショートステイ利用手続きを迅速に行えるようにする |
| 入浴支援を定期的に受けたい | 定期的な入浴により衛生面が維持される | ショートステイ利用時に週2回以上の入浴ができるようにする |
| 本人の体力低下を予防したい | 身体機能の低下を予防し、在宅生活を維持する | 滞在中にリハビリ体操に参加できるようにする |
| 医療的ケア(服薬・処置)を継続したい | 必要な医療ケアが滞らず提供される | ショートステイ利用時も服薬管理が確実に行われる |
| 家族旅行中の安心な預け先を確保したい | 家族旅行時も安心して本人が生活できる | 旅行期間中にショートステイを安全に利用できる体制を整える |
| 本人の生活意欲を高めたい | 日々の活動に前向きに取り組めるようになる | 滞在中に趣味活動やレクリエーションに参加する機会を持つ |
| 在宅介護に備えたレスパイト利用を定着させたい | 定期的なレスパイト利用で、介護負担を軽減し続けられる | 3ヶ月以内にレスパイト目的のショートステイ利用を開始する |
| 季節行事を楽しみたい | 季節行事を通じて生活に潤いを持たせる | 滞在中に季節イベントに1回以上参加できるよう支援する |
| 認知症による不安や混乱を軽減したい | 安心して過ごせる時間が増え、不安感が軽減する | ショートステイ利用中に不安行動が減少するよう支援する |
| 家庭内の介護力の限界を超えないよう支援したい | 家族の負担を調整しながら、在宅生活を続けられる | ショートステイ利用後、家族の疲労度をモニタリングし、必要に応じ利用回数を調整する |
【認知症重度者向け】ショートステイ利用に関するニーズ・長期目標・短期目標例文一覧
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 昼夜逆転が進み、家族の負担が増している | 生活リズムを整え、夜間安眠できる時間が増える | ショートステイ利用中も日中活動し夜間眠れる支援を行う |
| 徘徊傾向があり家族対応が困難 | 安全な環境で生活し、事故や迷子を防ぐ | ショートステイ利用中は施設内で安全に過ごせるよう支援する |
| 幻覚・妄想が頻発し、家族が精神的に疲弊している | 本人・家族ともに精神的安定を図る | ショートステイで穏やかに過ごせる日を月2回確保する |
| 食事拒否が見られ、栄養状態が心配 | 必要な栄養摂取を継続できるよう支援する | ショートステイ滞在中、1日3食の摂取を目指す |
| トイレ誘導が困難で失禁が増加している | 排泄ケアを安定して受けられる環境を整える | ショートステイ滞在中、トイレ誘導を定時に実施する |
| 感情の起伏が激しく、介護者が不安定 | 本人の情緒を安定させ、家族の安心を確保する | ショートステイ中に落ち着いて過ごせる時間を持つ |
| 生活環境の変化に強い混乱を示す | 環境変化への適応力を少しずつ高める | ショートステイ利用を2回経験し、施設職員に馴染めるよう支援する |
| 家族以外の支援者との関わりが少ない | 他者との交流に慣れ、安心感を得られる | ショートステイ中に職員と笑顔で会話する場面を作る |
| 不安から暴言や拒否が強まっている | 不安を軽減し、安心して過ごせる環境を整える | ショートステイ滞在中、安心できる声かけを心がける |
| 興奮が激しく家族の身体的負担が大きい | 興奮エピソードを減らし、落ち着いて生活できるようにする | ショートステイ中、興奮時に適切な対応を行い負担軽減を図る |
| 物取られ妄想が頻繁に出現している | 不安の軽減と信頼関係の構築を目指す | ショートステイ中、本人の訴えに共感的対応を行う |
| 繰り返しの呼び出しに家族が疲弊している | 本人の安心感を高めることで呼び出し行動を減らす | ショートステイ利用で安心感を得られるよう支援する |
| 自宅での危険行動(火の不始末など)が増えている | 安全な環境で過ごし、事故リスクを減らす | ショートステイ滞在中、安全確認と声かけを徹底する |
| 服薬管理が困難になっている | 必要な薬剤を確実に内服できる環境を整える | ショートステイ中に服薬介助を実施する |
| 介護拒否が見られるため在宅介護が困難 | 信頼できる支援者と関係を築き、介助受容を促す | ショートステイ利用中に受け入れ可能な介助方法を探る |
| 過去の記憶に固執し現実認識が低下している | 穏やかな気持ちで過ごし混乱を最小限にする | ショートステイ中に本人の話に寄り添う支援を行う |
| 感情表出が乏しくなってきた | 感情表出の機会を増やし、生活意欲を高める | ショートステイ滞在中、本人の好きな活動に誘導する |
| 家族が限界を迎えているが施設入所には抵抗がある | 在宅介護継続に向けた環境調整を行う | 定期的なショートステイ利用で家族負担を調整する |
| 食事形態の調整(きざみ、ミキサー食)が必要になった | 適切な食事形態で安全に食事ができるよう支援する | ショートステイ利用時に適正食形態を確認し提供する |
| 体重減少がみられ、栄養リスクが懸念される | 栄養管理を適切に行い体重減少を予防する | ショートステイ利用中の食事摂取状況を定期確認する |
【医療ニーズありケース向け】ショートステイ利用に関するニーズ・長期目標・短期目標例文一覧
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 服薬管理が本人のみでは難しい | 医療的な管理下で適切な服薬を継続できる | ショートステイ中に服薬管理を支援し、内服ミスを防止する |
| インスリン自己注射が不安定である | 安心してインスリン管理を受けられるようにする | ショートステイ滞在中に看護職員による注射支援を受ける |
| 定期的な褥瘡ケアが必要である | 褥瘡の悪化を防ぎ、状態を安定させる | ショートステイ中に褥瘡の観察と適切な処置を行う |
| 酸素療法を在宅で続けている | 酸素療法を安全に継続し、呼吸状態を維持する | ショートステイ利用時も酸素管理が適切に行われる |
| 尿カテーテル管理が必要である | 清潔・安全なカテーテル管理を行い感染予防を図る | ショートステイ中にカテーテルケアを確実に実施する |
| 定期的な吸引が必要である | 呼吸管理を適切に行い、窒息リスクを防止する | ショートステイ滞在中、必要時に吸引が適切に行われる |
| PEG(胃ろう)管理が必要である | 適切な栄養管理により健康を維持する | ショートステイ中に安全に経管栄養が実施できる |
| 人工肛門(ストーマ)の管理が必要である | ストーマ管理を安全に行い生活の質を維持する | ショートステイ滞在中にストーマケアを支援する |
| 血糖コントロールが不安定である | 血糖値の安定を図り、健康を維持する | ショートステイ利用中に血糖測定と指示に基づく対応を行う |
| 心疾患により急変リスクがある | 急変時にも迅速に対応できる体制を確保する | ショートステイ利用前に緊急対応マニュアルを作成する |
| 感染症へのリスク管理が必要である | 集団生活でも感染予防策を徹底する | ショートステイ中に感染予防策(手洗い・換気)を徹底する |
| 癌の疼痛コントロールが必要である | 痛みの少ない生活を目指す | ショートステイ利用時に医師指示に基づく疼痛緩和を行う |
| 高血圧・心不全による塩分管理が必要である | 適切な食事療法により症状悪化を予防する | ショートステイ滞在中も減塩食を提供する |
| 透析治療を継続している | 透析治療と在宅生活の両立を支援する | 透析日に送迎・スケジュール調整を行うショートステイを利用する |
| 抗がん剤治療中で副作用管理が必要である | 副作用に配慮しながら安全な生活を支援する | ショートステイ滞在中に副作用観察を強化する |
| 慢性疼痛への対応が必要である | 痛みに配慮し、QOL(生活の質)を高める | ショートステイ利用時に疼痛緩和ケアを行う |
| 医療的処置への本人理解が難しい | 本人の不安を軽減し、安心して処置を受ける | ショートステイ中、やさしい声掛けと説明で処置を支援する |
| 定期的なバイタルチェックが必要である | バイタルサイン異常の早期発見・対応を目指す | ショートステイ利用時にバイタルチェックを毎日実施する |
| 麻薬管理(痛み止め使用)が必要である | 適切な麻薬管理で安全に疼痛緩和を図る | ショートステイ滞在中に薬剤管理者が確実に管理する |
| 移動・移乗介助時に医療的注意が必要である | 事故防止と安全確保を図る | ショートステイ利用時に移動・移乗介助マニュアルを活用する |
【家族関係に課題があるケース向け】ショートステイ利用に関するニーズ・長期目標・短期目標例文一覧
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 介護負担を巡り家族間の対立が生じている | 家族間の介護に対する理解と協力体制を築く | ショートステイ利用により家族の心身負担を一時的に軽減する |
| 主介護者が孤立し精神的に追い詰められている | 介護者が適切に休息とサポートを得られるようにする | 月1回ショートステイを利用し介護者がリフレッシュできる機会を作る |
| 家族が本人に怒りをぶつける場面が見られる | 家族と本人双方の精神的負担を軽減する | 定期的なショートステイ利用により家庭内緊張を和らげる |
| 家族が本人の介護拒否に困惑している | 第三者の介入により介護受容を支援する | ショートステイ利用中、介助受容のための関わり方を探る |
| 過干渉な家族による本人の自立阻害が見られる | 本人の自立支援と家族の関与調整を図る | ショートステイ中に本人主体の生活場面を作る |
| 本人と家族の意思疎通が困難になっている | 本人の意向を尊重した支援体制を整える | ショートステイ利用時に本人の希望確認を積極的に行う |
| 介護方針を巡って家族内で意見が対立している | 家族の話し合いを促し、方針を整理する | ショートステイ利用中に担当者会議で家族意向を整理する |
| 家族が本人への接し方に悩んでいる | 本人に適した接し方を学び、実践できるようにする | ショートステイ職員から家族へ接し方のアドバイスを行う |
| 介護を担う家族が複数おり負担が不公平になっている | 介護分担の見直しを促す | ショートステイ利用による介護負担の一時調整を行う |
| 家族が本人の病状を受け入れられていない | 病状理解を深め、現実に向き合えるよう支援する | ショートステイ利用中に医療・介護職による説明機会を作る |
| 家族に虐待リスクが懸念される | 本人を安全に保護し、家族への介護支援も検討する | ショートステイ利用で本人の安全確保を図る |
| 家族が支援拒否をしており孤立している | 外部支援機関との連携を図る | ショートステイ利用をきっかけに地域資源を紹介する |
| 経済的負担を理由に家族が介護を放棄している | 支援制度利用を促し介護継続を支える | ショートステイ利用と併せて公的支援制度を活用する |
| 世代間で介護意識に差があり協力できていない | 世代間理解を促進し、介護負担の共有を目指す | 担当者会議等で家族の意見を整理する機会を設ける |
| 介護者が心身不調を訴えているが休めない | 介護者が休息を取り介護継続意欲を維持する | 月1〜2回のショートステイ利用で介護者休養日を確保する |
| 本人が家族に依存しすぎている | 本人の自己決定と主体性を支援する | ショートステイ中に本人自身で選択する機会を増やす |
| 離れて暮らす家族が本人の状況を理解していない | 本人の現状を家族が正しく把握する | ショートステイ利用中に状況報告を行う |
| 介護放棄に至る危険性が高まっている | 介護支援体制を強化し継続支援を図る | ショートステイ定期利用と合わせ地域包括支援センターと連携する |
| 家族が高齢で介護に限界を感じている | 本人・家族ともに持続可能な介護体制を目指す | ショートステイ利用頻度を増やし介護負担軽減を図る |
| 介護に関する家族間の連携不足が目立つ | 介護に対する情報共有と協力体制を構築する | ショートステイ利用前後に家族間で状況確認を行う |
【終末期に向かうケース向け】ショートステイ利用に関するニーズ・長期目標・短期目標例文一覧
| 生活全般の解決すべき課題(ニーズ) | 長期目標 | 短期目標 |
|---|---|---|
| 終末期に向けた心身の安寧を保ちたい | 安心して穏やかな日々を過ごす | ショートステイ利用中に苦痛の緩和を最優先する |
| 本人が「最期まで自宅で過ごしたい」と希望している | 本人の希望を尊重し在宅生活を支える | 必要時にショートステイを活用し、在宅継続を支援する |
| 疼痛緩和が必要となってきた | 苦痛の少ない日々を送る | ショートステイ滞在中に疼痛コントロールを確実に行う |
| 意識の低下が見られ介護負担が増している | 適切な支援体制で本人・家族を支える | ショートステイ利用により介護力を補完する |
| 食事摂取量が著しく低下してきた | 本人の意思を尊重しつつ栄養管理を行う | ショートステイ中に無理のない食事支援を行う |
| 呼吸苦が出現してきた | 呼吸緩和ケアを実施し安楽な生活を目指す | ショートステイ利用時に酸素管理と呼吸介助を強化する |
| 医療的処置(吸引・酸素投与等)が必要になった | 医療ニーズに応じた適切なケアを受ける | ショートステイ滞在中も医療的ケアを確実に実施する |
| 家族が看取りに対する不安を抱えている | 家族の精神的支援を行い看取りに備える | ショートステイ利用時に看取りケアの説明と相談支援を行う |
| 本人が不安を訴えることが増えてきた | 精神的な安定を図る | ショートステイ中に安心できる声かけ・対応を徹底する |
| せん妄状態が頻発している | 本人の安心感を高め症状緩和を図る | ショートステイ中に環境調整と見守りを強化する |
| 排泄ケアの介助量が増加している | 適切な排泄支援で本人の尊厳を守る | ショートステイ滞在中に排泄介助を丁寧に行う |
| 意思疎通が難しくなってきた | 非言語的コミュニケーションで本人理解を図る | ショートステイ中に表情・反応を観察しニーズを把握する |
| 介護者の心身負担が限界に達している | 家族の休養と精神的支援を図る | 定期的なショートステイ利用で家族に休息時間を提供する |
| 施設入所を検討しているが本人の希望もあり悩んでいる | 本人の尊厳を尊重し最適な選択を支援する | ショートステイ利用しながら今後の生活方針を検討する |
| 急変時対応への備えが不十分で不安である | 緊急対応マニュアルを整備する | ショートステイ前に緊急時対応計画を作成する |
| 看取り期に向けた本人・家族の心構えができていない | 終末期支援体制を整え本人・家族に寄り添う | ショートステイ中に看取りケアに関する支援を開始する |
| 意欲低下が著しく活動量が減少している | 本人のペースに合わせた生活支援を行う | ショートステイ中に無理なく好きな活動に誘導する |
| 家族が最期の時間を大切に過ごしたいと希望している | 本人と家族が共に穏やかな時間を過ごせるよう支援する | ショートステイ利用後、在宅での家族支援を強化する |
| 終末期ケアに関する家族の知識不足が見られる | 家族への情報提供と心構え支援を行う | ショートステイ利用時に看護職から終末期ケアの説明を行う |
| 尊厳ある最期を迎えたいという本人の希望がある | 本人の尊厳を尊重したケアを提供する | ショートステイ中も本人の意向に沿った支援を行う |
2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。介護保険の居宅サービス介護給付費単位数の改定内容
- 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 通所介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 短期入所生活介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧
- 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧
施設サービス等介護給付費単位数の改定内容
- 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
地域密着型サービスの単位数改定内容
- 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
- 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧
介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容
2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
- 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件
- 生産性向上推進体制加算の算定要件
- 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説!
- 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」
- 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件
- 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説!